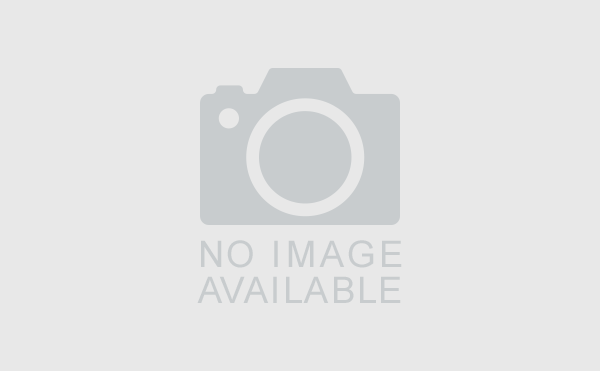廃業するなら幸せな廃業を目指せ!

日刊現代DIGITAL、「廃業・解散の急増で注目される“社長のおくりびと”の仕事とは?」という記事(2019年10月31日)から。
倒産が減少傾向にある一方、休廃業が大幅に増加していることをご存知だろうか?
いわゆる倒産が減少しているのは、記事にあるとおり、『政府が行う景気維持対策のリスケジュール(借入返済資金の猶予)など、倒産抑制策が効果を発揮しているため』だと思う。
また、休廃業が大幅に増加している理由として、
『高齢化や後継者不足など、業績は順調でも事業継承がうまくいかない中小企業が増えてきていることです。業績がいい今なら、廃業しても従業員の給与が払え、自身の老後資金も残せると廃業の決断をしているんです』
と記事には書かれている。
もちろん、これもよく言われていることであり、そうなのだろう。
しかし、記事にあるような「恵まれた」中小企業はどのくらいあるのだろう?
つまり、
- 業績は順調で
- 廃業しても従業員に給料(退職金?)が払えて
- さらに、自分の老後資金まで確保できるが
事業を承継する人がいないため廃業せざるを得ない中小企業だ。
実は、休廃業のデータは休業・廃業・解散を合計したものであり、それぞれの比率はわからない。
だから、廃業の中には、後継者はいるものの、このまま続けてもさらに悪い状況になるから廃業したという企業もあるだろう。
また、廃業したくても債務などで今はできない(他で働いた方が安定収入がある)ため休業する中小企業もあるだろう。
そもそも、政府の倒産抑制政策のため、倒産が減少しているなら、倒産寸前の企業が休廃業のデータに含まれているだろう。
このような企業は、記事あるような幸せな廃業はなかなか難しいだろう。
結局、廃業するにしても「幸せな廃業」をするためには、記事にあるように、
- 早めに準備を始める
- 思い切って撤退を決断する
- 終結までの計画性を持った立ち居振る舞い
- 関係者との利害調整の工夫
- 経営や法律、財務税金、手続きへの広い視野
- 未知な未来に挑む勇気。
特に、1と3は重要なことであると思う。
なお、当事務所のオウンドメディアである「あきんどう」で起業の出口戦略や廃業についての記事を書いていますので、ご興味ある方は参考にしてほしい。